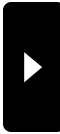2010年08月31日
弁護士も認めている江藤の実績
以前のブログで小生が同級生に「江藤新平をNHKの大河ドラマの主人公にしたい…」と話したことは書きました。
http://sagawokakeru.sagafan.jp/e260100.html
この中に弁護士がいますが、彼は佐賀県の弁護士で指導的な役割を担っている人です。
その彼が『江藤新平の実績はすごい…』と語っていました。
彼曰く、江藤は「一般の人たちがモノを言える風土をつくった。これは凄いことだ」ということでした。
このブログでも書いてきましたが、江藤の凄さとは彼の死後百年以上経った現代でもトップクラスをいくような理念を、あの状況の中で考えていたということです。
そして、われわれが享受している民主主義という素晴らしいシステムを、江藤はいち早く確立しようと懸命になっていたということでしょう。
彼が23歳の時に書いた『図海策』を読んでもその先見の明がよく分かります。
江藤の理念は、当時はまったく考えられなかった「情報公開」にも目が行っています。この凄さを、大河ドラマという形で全国に広げたいと思っています。
http://sagawokakeru.sagafan.jp/e260100.html
この中に弁護士がいますが、彼は佐賀県の弁護士で指導的な役割を担っている人です。
その彼が『江藤新平の実績はすごい…』と語っていました。
彼曰く、江藤は「一般の人たちがモノを言える風土をつくった。これは凄いことだ」ということでした。
このブログでも書いてきましたが、江藤の凄さとは彼の死後百年以上経った現代でもトップクラスをいくような理念を、あの状況の中で考えていたということです。
そして、われわれが享受している民主主義という素晴らしいシステムを、江藤はいち早く確立しようと懸命になっていたということでしょう。
彼が23歳の時に書いた『図海策』を読んでもその先見の明がよく分かります。
江藤の理念は、当時はまったく考えられなかった「情報公開」にも目が行っています。この凄さを、大河ドラマという形で全国に広げたいと思っています。
2010年08月31日
独眼竜政宗の画期的な手法
空前の大ヒットとなったNHK大河ドラマ『独眼流政宗』では、俳優の演出の仕方もユニークです。
ウィキペディア『独眼竜政宗』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%9C%BC%E7%AB%9C%E6%94%BF%E5%AE%97_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)
[上記サイトから記事一部転載]
また、「渡辺謙=知名度は高くない若手」、「勝新太郎=衆目の知るところの大御所」という図式が、そのまま「政宗=奥羽の若き大名」、「秀吉=老成した天下人」にも当てはまるなど、役者の立場・イメージと演じる役の立場がぴったりという印象が強いのも特徴である。配役決定後、渡辺は勝に事前に挨拶しておこうとしたが、勝は「小田原で政宗が秀吉と初めて出会うのなら、渡辺と勝もそのシーンの撮影まで会うべきでない」と主張。撮影は渡辺と勝が会うことがないよう調整して行われ、小田原での対面シーン本番で初めて二人は実際に顔を合わせた。奥羽では暴れ放題であった政宗が秀吉を前に平伏する姿は、奔放に振る舞っていた若い俳優が、ベテランを前にして自分の小ささを思い知らされているようであり、そのリアルな緊張感が画面からも伝わってくる名シーンとなった。このシーンの収録後、渡辺は勝から「いい眼をしていたぞ…」との声をかけてもらったという。まさに「渡辺=政宗」が「勝=秀吉」に認められたという、シーンそのままの構図が実際の収録現場にも当てはまったのである。そしてその「渡辺=政宗」は次第に勝や家康役の津川雅彦とも対等に渡り合うようになり、政宗と共に渡辺も俳優として成長している様子がリアルに感じられた。[転載了]
さらに驚いたのは臨終した政宗のシーンの後、実際の政宗の遺骨が紹介される映像。これは、本物の映像でした。
参照:http://www.youtube.com/watch?v=4yi9UN7PwTA
[上記サイトから記事一部転載]
最も斬新な演出の一つとして、伊達政宗本人の遺骨が映像として紹介された。政宗墓所・瑞鳳殿は第二次大戦時の仙台空襲で焼失、1979年(昭和54年)に再建されたが、それに先立ち1974年(昭和49年)に行われた発掘調査で発見されたもので、年月が経過していたにも拘らず、奇跡的に残っており、科学的鑑定により生前の政宗の容貌・体格・血液型なども推定できた。本作ではそれらを第1話のアバンタイトルで紹介し、最終回ラストで発掘調査の映像と政宗本人の頭蓋骨を再び映して物語は幕を閉じる。[転載了]
ウィキペディア『独眼竜政宗』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%9C%BC%E7%AB%9C%E6%94%BF%E5%AE%97_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)
[上記サイトから記事一部転載]
また、「渡辺謙=知名度は高くない若手」、「勝新太郎=衆目の知るところの大御所」という図式が、そのまま「政宗=奥羽の若き大名」、「秀吉=老成した天下人」にも当てはまるなど、役者の立場・イメージと演じる役の立場がぴったりという印象が強いのも特徴である。配役決定後、渡辺は勝に事前に挨拶しておこうとしたが、勝は「小田原で政宗が秀吉と初めて出会うのなら、渡辺と勝もそのシーンの撮影まで会うべきでない」と主張。撮影は渡辺と勝が会うことがないよう調整して行われ、小田原での対面シーン本番で初めて二人は実際に顔を合わせた。奥羽では暴れ放題であった政宗が秀吉を前に平伏する姿は、奔放に振る舞っていた若い俳優が、ベテランを前にして自分の小ささを思い知らされているようであり、そのリアルな緊張感が画面からも伝わってくる名シーンとなった。このシーンの収録後、渡辺は勝から「いい眼をしていたぞ…」との声をかけてもらったという。まさに「渡辺=政宗」が「勝=秀吉」に認められたという、シーンそのままの構図が実際の収録現場にも当てはまったのである。そしてその「渡辺=政宗」は次第に勝や家康役の津川雅彦とも対等に渡り合うようになり、政宗と共に渡辺も俳優として成長している様子がリアルに感じられた。[転載了]
さらに驚いたのは臨終した政宗のシーンの後、実際の政宗の遺骨が紹介される映像。これは、本物の映像でした。
参照:http://www.youtube.com/watch?v=4yi9UN7PwTA
[上記サイトから記事一部転載]
最も斬新な演出の一つとして、伊達政宗本人の遺骨が映像として紹介された。政宗墓所・瑞鳳殿は第二次大戦時の仙台空襲で焼失、1979年(昭和54年)に再建されたが、それに先立ち1974年(昭和49年)に行われた発掘調査で発見されたもので、年月が経過していたにも拘らず、奇跡的に残っており、科学的鑑定により生前の政宗の容貌・体格・血液型なども推定できた。本作ではそれらを第1話のアバンタイトルで紹介し、最終回ラストで発掘調査の映像と政宗本人の頭蓋骨を再び映して物語は幕を閉じる。[転載了]
2010年08月31日
大河ドラマの定番のネタ…
NHK大河ドラマの定番のネタの一つに、三傑(織田信長、豊臣秀吉、徳川家康)がありますが、これを題材に選ぶ側としたら安心感があるのでしょうね。
つまり、皆がこの三傑のことを知っているという“安心感”が…。
大河ドラマにおいては、この三傑の配役が重要なポイントなりますが、ひとりの俳優がそれぞれの家系に関わる人を演じたら、長く大河ドラマを見ている人は混乱するする場合もあるでしょうね…。
大河ドラマにおいては、徳川家康を2回演じた津川雅彦さんが印象が強いですね…。
「独眼流政宗」と「葵徳川三代」でともに徳川家康役でした。二つの作品ともジェームス三木さんが脚本家なので、そういうキャストになったのかもしれませんね。
つまり、皆がこの三傑のことを知っているという“安心感”が…。
大河ドラマにおいては、この三傑の配役が重要なポイントなりますが、ひとりの俳優がそれぞれの家系に関わる人を演じたら、長く大河ドラマを見ている人は混乱するする場合もあるでしょうね…。
大河ドラマにおいては、徳川家康を2回演じた津川雅彦さんが印象が強いですね…。
「独眼流政宗」と「葵徳川三代」でともに徳川家康役でした。二つの作品ともジェームス三木さんが脚本家なので、そういうキャストになったのかもしれませんね。
2010年08月30日
近松門左衛門
NHK大河ドラマのストーリーテラーをたくみに使うのは脚本家のジェームス三木さんですが、『八代将軍吉宗』では、近松門左衛門(江守徹)がこれを務めています。
以下、ウィキペディア『八代将軍吉宗』から転載です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%B0%86%E8%BB%8D%E5%90%89%E5%AE%97
[上記サイトから記事一部転載]
江守徹演じる近松門左衛門がナレーションと史実を解説させるキャラクターとしている試みが最大の特色で、家系図や享保改革などについてパネルや表を使い、時には「パーティ」「ドラマ」といった現代語も交えてわかりやすく説明させている。同様の手法は2000年の『葵徳川三代』でも用いられている(この時は中村梅雀演じる徳川光圀が語り・解説役)。近松は吉宗在世中の享保9年(1724年)に死去しており、以降は「幽霊」として登場。最終回では天国で吉宗と吉宗の父・光貞に1995年当時までの日本の世相を教えた。「さればでござる」のセリフが近松のキャッチフレーズだった。最終回から一週間後の12月17日には「さればでござる・全て見せます大河ドラマ」という特別番組が放送され、これまでの大河ドラマの歴史を振り返り、さらに翌年の大河ドラマ「秀吉」の主演・竹中直人によるミニコントも放送された。番組のナビゲーターはタイトルからも分かるとおり、近松役の江守徹と、近松家の少女(お梶)役・遠野凪子が務めた。[転載了]
こうした独特の手法はジェームス三木さんの独壇場ですね…。
以下、ウィキペディア『八代将軍吉宗』から転載です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%B0%86%E8%BB%8D%E5%90%89%E5%AE%97
[上記サイトから記事一部転載]
江守徹演じる近松門左衛門がナレーションと史実を解説させるキャラクターとしている試みが最大の特色で、家系図や享保改革などについてパネルや表を使い、時には「パーティ」「ドラマ」といった現代語も交えてわかりやすく説明させている。同様の手法は2000年の『葵徳川三代』でも用いられている(この時は中村梅雀演じる徳川光圀が語り・解説役)。近松は吉宗在世中の享保9年(1724年)に死去しており、以降は「幽霊」として登場。最終回では天国で吉宗と吉宗の父・光貞に1995年当時までの日本の世相を教えた。「さればでござる」のセリフが近松のキャッチフレーズだった。最終回から一週間後の12月17日には「さればでござる・全て見せます大河ドラマ」という特別番組が放送され、これまでの大河ドラマの歴史を振り返り、さらに翌年の大河ドラマ「秀吉」の主演・竹中直人によるミニコントも放送された。番組のナビゲーターはタイトルからも分かるとおり、近松役の江守徹と、近松家の少女(お梶)役・遠野凪子が務めた。[転載了]
こうした独特の手法はジェームス三木さんの独壇場ですね…。
2010年08月30日
図海策
江藤新平が1856年に執筆した「図海策」ですが、それまで攘夷論を展開していた江藤の“気付き”が見られるものです。
この「図海策」とは、形勢・招才・通商・拓北の四章からなり、当時の日本の政策論を展開しています。この中で江藤は「開国通商、富国強兵の必要性」などを述べています。
国立国会図書館所蔵のデータでこの「図海策」のデータを見つけて読んでみました。
以下に一部を抜粋します。
[図海策一部]
日本の邦たる四方皆生みなるを以て。備べき所は甚た廣くして。海防の手段最も施し難き国なる故に。守て戦ふなどヽは。敗亡の基にして。最も失策なり。唯良策と云は。先つ當今の強国と和親を結ひ。宇内の賢才を招て其用を給さしめ軍艦を購ふて海戦を練習し通商を盛んにして国家を富すに在り。国家己に富み。海戦既に熟し。然る後に檄を各国に傅へて。無道の国を攻む可し。且蝦夷を開拓して北方に通商の府を築き。傍ら西洋各国の會盟に参興し。弱を助け強を抑へ。義に興し不義を撃ち。魏然として天下の依頼する所と為らば。宇内自ら日本に帰せん。
これを読んで、当時の江藤の見識の広さを改めて感じました。
と、同時にNHK大河ドラマに江藤新平を主人公にするのであれば、この「図海策」ははずすことができませんね。
2010年08月30日
江藤新平のスピード感
幕末から明治維新にかけての時代と現代とでは、情報伝達のスピードが明らかに異なりなります。
明治維新の歴史を読むにつけ、いつも驚かされるのは、鎖国を貫いてきた江戸時代からいきなり外国船の来航を経て、激動の時代となり、ここまで短い時間で、近代国家の基礎を作った日本人って。日本人って凄いなぁ~と思います。
この『答え』を出すには、小生自身もっともっと歴史を学ばなければなりませんが、今の時点で言えることは、こうした「超」が付くくらいの変革の時代(明治維新)において、これらの中でも「江藤新平のスピード感」は群を抜いています。
もし江藤が今の時代に生きていたら…。
彼の情報収集能力とその本質を見極める力、さらに時代を先取りした政策を打ち出す力は、日本でナンバーワンになることでしょう。
江藤は海外留学経験がありませんが、司法卿時代にはフランスの法体系を研究して法制度の根本を決めました。
司法制度の整備(司法職務制定・裁判所建設・民法編纂・国法編纂など)に功績を残しました。
また、民権論者としても有名で、「娼妓解放令」、民衆に行政訴訟を認めたことも知られています。
江藤は「事の本質を見極める能力」がものすごく高いので、こうしたスピード感をもっての行動ができるんでしょうね。
明治維新の歴史を読むにつけ、いつも驚かされるのは、鎖国を貫いてきた江戸時代からいきなり外国船の来航を経て、激動の時代となり、ここまで短い時間で、近代国家の基礎を作った日本人って。日本人って凄いなぁ~と思います。
この『答え』を出すには、小生自身もっともっと歴史を学ばなければなりませんが、今の時点で言えることは、こうした「超」が付くくらいの変革の時代(明治維新)において、これらの中でも「江藤新平のスピード感」は群を抜いています。
もし江藤が今の時代に生きていたら…。
彼の情報収集能力とその本質を見極める力、さらに時代を先取りした政策を打ち出す力は、日本でナンバーワンになることでしょう。
江藤は海外留学経験がありませんが、司法卿時代にはフランスの法体系を研究して法制度の根本を決めました。
司法制度の整備(司法職務制定・裁判所建設・民法編纂・国法編纂など)に功績を残しました。
また、民権論者としても有名で、「娼妓解放令」、民衆に行政訴訟を認めたことも知られています。
江藤は「事の本質を見極める能力」がものすごく高いので、こうしたスピード感をもっての行動ができるんでしょうね。
2010年08月30日
江藤新平の永蟄時代
幕末の志士の中で江藤新平は“遅咲き”と言えるでしょう。
1834年生まれの江藤は、同じ時代に活躍した人と比べると…。
桂小五郎は江藤より一つ上。吉田松陰は4歳上。
坂本龍馬は二つ下、高杉晋作は5つ下。
江藤が脱藩して京都に上ったのが1862年で28歳です。
この時には吉田松陰は既に斬首されていてこの世にいません。
江藤は脱藩の罪を問われて、運よく死罪は免れたものの、永蟄(無期の謹慎)となり、再び表舞台に出るのは、1867年12月に郡目付として復帰してからです。
江藤の蟄居の間、高杉晋作は27歳で亡くなり、坂本龍馬も31歳で暗殺されています。
大河ドラマで江藤新平を主人公にする以上、シナリオとしては江藤の雌伏の時代をどう描くか…が大きなポイントとなります。
小生のここまでのプランでは、ストーリーテラーを妻の千代子にしようと思っていますが、この間は、江藤の目を通じて幕末から明治へ動きを捉えてもいいかと思っています。
蛇足ですが、復帰後の江藤の活躍は目覚しいものあり、あっという間に全国でトップレベルの政策実行者になります。
江藤のような人生はほかに例がなく、ドラマ上の演出もいろいろなものが考えられますね。
1834年生まれの江藤は、同じ時代に活躍した人と比べると…。
桂小五郎は江藤より一つ上。吉田松陰は4歳上。
坂本龍馬は二つ下、高杉晋作は5つ下。
江藤が脱藩して京都に上ったのが1862年で28歳です。
この時には吉田松陰は既に斬首されていてこの世にいません。
江藤は脱藩の罪を問われて、運よく死罪は免れたものの、永蟄(無期の謹慎)となり、再び表舞台に出るのは、1867年12月に郡目付として復帰してからです。
江藤の蟄居の間、高杉晋作は27歳で亡くなり、坂本龍馬も31歳で暗殺されています。
大河ドラマで江藤新平を主人公にする以上、シナリオとしては江藤の雌伏の時代をどう描くか…が大きなポイントとなります。
小生のここまでのプランでは、ストーリーテラーを妻の千代子にしようと思っていますが、この間は、江藤の目を通じて幕末から明治へ動きを捉えてもいいかと思っています。
蛇足ですが、復帰後の江藤の活躍は目覚しいものあり、あっという間に全国でトップレベルの政策実行者になります。
江藤のような人生はほかに例がなく、ドラマ上の演出もいろいろなものが考えられますね。
2010年08月30日
佐賀の乱に参加した少年兵
以前のブログで、江藤新平の孫の江藤冬雄さんの佐賀新聞での連載のことを書きました。
http://sagawokakeru.sagafan.jp/e263303.html
この江藤冬雄さんの記事には、小生の祖先も登場しています。
母の曽祖父の横尾孫作ですが、佐賀の乱(佐賀戦争)において、少年兵として出兵しています。
連載の中で、孫作と同じ少年兵の生き残り古賀廉造との絡みについて面白い記述があります。
佐賀新聞 1974年4月5日の記事から
【田手川の激戦には、古賀廉造さんに、横尾孫作さんも決死奮戦、九死に一生を得た人である。(略)
昭和9年の中秋のある夜、万部島招魂場事務所の座敷に久々にご帰郷の大先輩古賀廉造さんを迎えて、酒宴となった。古賀さんは、横尾孫作さんと愉快気に祝杯を重ねておられたが、急に我々の方に向き直り、横尾さんを指し、
「おいっ、この横尾、今、かくのごとく、おれと仲よく、酒のみするが、この男、おれを殺そうとした男だぞ」と言われたので、満座びっくりして横尾さんの顔を見た。横尾さんもけげんな顔をして
「私が。あたなを殺そうとした。いったいそれは、なんのことですか」といかにも腑に落ちぬ風であった。
古賀さんは、からからと打ち笑い、横尾さんに向かい、
「おい、横尾君。何をとぼけた顔をしよるか。忘れたか、佐賀戦争の時を。明治7年2月15日、おまえと一緒に、高木瀬の家を出て佐賀に行く時、その道々、さあ、これから戦争じゃが、討ち死にして、首を官軍の士民兵士に、とられては、末代までの恥だ。おれが討たれたら、貴様、俺の首を切って、古賀家代々の墓に埋めてくれ。貴様が討たれたら、おれが貴様の首を切って、横尾家の菩提寺に葬ってやると、我輩が言ったら、足下(※貴殿のこと)は、合点だと言って、その時二人かたく約束したじゃないか。
その翌日の未明から、佐賀城の攻防戦、以来、各所の激戦を経て2月23日、田手川の大激戦の事を、足下、忘れてはおらぬだろう。我輩が足を撃たれて、しまったと絶叫して、転倒したら、足下は、振り向きさま、“古賀、安心しろ。貴様の首は、拙者が、古賀家の菩提寺に葬ってやる”と言って、まさにわが輩の首を切らんとしたではないか。
その時だけは、実際びっくり仰天、ま、ま、まってくれ、待ってくれ、まだ、おれは死にはせぬ。これ位お傷が何だ。刀はおろせ、刀はおろせと言ったので、足下はわが輩を斬るのを、やめたじゃないか、はっはははー」
と愉快気に笑われた。横尾孫作さん、目を閉じ、沈吟やや久しくあったが、はっとしたように顔をあげニコリとして、「うーむ、そんな事があったな」とうなずき、献酬しきり、実に豪華な酒宴、これぞ、つわものどもの秋の宴、40年経過した今日今なお忘れ得ざる思い出である。】
今、こうして75年前の宴の話を読んでいて、小生の祖先の横尾がもし、この激戦で死んでいたら、小生は生まれていません…。
そう考えると、運命とはいえ佐賀の乱は“他人事”ではありませんでした。
http://sagawokakeru.sagafan.jp/e263303.html
この江藤冬雄さんの記事には、小生の祖先も登場しています。
母の曽祖父の横尾孫作ですが、佐賀の乱(佐賀戦争)において、少年兵として出兵しています。
連載の中で、孫作と同じ少年兵の生き残り古賀廉造との絡みについて面白い記述があります。
佐賀新聞 1974年4月5日の記事から
【田手川の激戦には、古賀廉造さんに、横尾孫作さんも決死奮戦、九死に一生を得た人である。(略)
昭和9年の中秋のある夜、万部島招魂場事務所の座敷に久々にご帰郷の大先輩古賀廉造さんを迎えて、酒宴となった。古賀さんは、横尾孫作さんと愉快気に祝杯を重ねておられたが、急に我々の方に向き直り、横尾さんを指し、
「おいっ、この横尾、今、かくのごとく、おれと仲よく、酒のみするが、この男、おれを殺そうとした男だぞ」と言われたので、満座びっくりして横尾さんの顔を見た。横尾さんもけげんな顔をして
「私が。あたなを殺そうとした。いったいそれは、なんのことですか」といかにも腑に落ちぬ風であった。
古賀さんは、からからと打ち笑い、横尾さんに向かい、
「おい、横尾君。何をとぼけた顔をしよるか。忘れたか、佐賀戦争の時を。明治7年2月15日、おまえと一緒に、高木瀬の家を出て佐賀に行く時、その道々、さあ、これから戦争じゃが、討ち死にして、首を官軍の士民兵士に、とられては、末代までの恥だ。おれが討たれたら、貴様、俺の首を切って、古賀家代々の墓に埋めてくれ。貴様が討たれたら、おれが貴様の首を切って、横尾家の菩提寺に葬ってやると、我輩が言ったら、足下(※貴殿のこと)は、合点だと言って、その時二人かたく約束したじゃないか。
その翌日の未明から、佐賀城の攻防戦、以来、各所の激戦を経て2月23日、田手川の大激戦の事を、足下、忘れてはおらぬだろう。我輩が足を撃たれて、しまったと絶叫して、転倒したら、足下は、振り向きさま、“古賀、安心しろ。貴様の首は、拙者が、古賀家の菩提寺に葬ってやる”と言って、まさにわが輩の首を切らんとしたではないか。
その時だけは、実際びっくり仰天、ま、ま、まってくれ、待ってくれ、まだ、おれは死にはせぬ。これ位お傷が何だ。刀はおろせ、刀はおろせと言ったので、足下はわが輩を斬るのを、やめたじゃないか、はっはははー」
と愉快気に笑われた。横尾孫作さん、目を閉じ、沈吟やや久しくあったが、はっとしたように顔をあげニコリとして、「うーむ、そんな事があったな」とうなずき、献酬しきり、実に豪華な酒宴、これぞ、つわものどもの秋の宴、40年経過した今日今なお忘れ得ざる思い出である。】
今、こうして75年前の宴の話を読んでいて、小生の祖先の横尾がもし、この激戦で死んでいたら、小生は生まれていません…。
そう考えると、運命とはいえ佐賀の乱は“他人事”ではありませんでした。
2010年08月30日
江藤の幼少期
50回に及ぶNHK大河ドラマですが、主人公の人生を時系列的に描きます。
江藤新平を主人公にした大河ドラマの場合、江藤の幼少期の描き方及びどのくらいの回数をそこに当てるかなどを考えています。
プロットについては別のブログでも、ぼちぼち書いているのですが、この段階(8月30日)ではまだ“設計図の前”程度です。
通常の大河ドラマの場合、幼少期は1回から2回でしょうが、小生はここをもう少し深くやってみようと思っています。
江藤が生まれたのは1834年。ペリー来航の約20年前ですが、ここから幕末の混乱と明治維新に向けての“体系的な流れ”をもう少し掘り下げたいと思っているからです。
佐賀においては七賢人の一人鍋島直正の藩政を描きたいと思っていますし、特に、佐賀藩の技術革新の礎となった鍋島の物の考え方や、江藤よりも少し先輩の佐野常民や枝吉神陽の話題も拾いたいところです。
そして、何よりも大きい存在が江藤の母親の浅子。佐賀藩士・浦忠左衛門の娘で当時としては珍しく、女性による寺子屋を開いていました。
浅子は近所の子供たちに「四書五経」なども教えていたそうです。
こうした母親の影響を江藤も少なからず受けたことでしょう。
このキャラクター(浅子)の存在を通して、当時に時代の“風景”“情勢”をもう少し深堀りしながら、佐賀藩以外の藩の動きなども組み合わせいければと思っています。
こうしたこともあり、江藤の幼少期はできれば3回まで引っ張ることができれば…面白い展開になるでしょうか?!
江藤新平を主人公にした大河ドラマの場合、江藤の幼少期の描き方及びどのくらいの回数をそこに当てるかなどを考えています。
プロットについては別のブログでも、ぼちぼち書いているのですが、この段階(8月30日)ではまだ“設計図の前”程度です。
通常の大河ドラマの場合、幼少期は1回から2回でしょうが、小生はここをもう少し深くやってみようと思っています。
江藤が生まれたのは1834年。ペリー来航の約20年前ですが、ここから幕末の混乱と明治維新に向けての“体系的な流れ”をもう少し掘り下げたいと思っているからです。
佐賀においては七賢人の一人鍋島直正の藩政を描きたいと思っていますし、特に、佐賀藩の技術革新の礎となった鍋島の物の考え方や、江藤よりも少し先輩の佐野常民や枝吉神陽の話題も拾いたいところです。
そして、何よりも大きい存在が江藤の母親の浅子。佐賀藩士・浦忠左衛門の娘で当時としては珍しく、女性による寺子屋を開いていました。
浅子は近所の子供たちに「四書五経」なども教えていたそうです。
こうした母親の影響を江藤も少なからず受けたことでしょう。
このキャラクター(浅子)の存在を通して、当時に時代の“風景”“情勢”をもう少し深堀りしながら、佐賀藩以外の藩の動きなども組み合わせいければと思っています。
こうしたこともあり、江藤の幼少期はできれば3回まで引っ張ることができれば…面白い展開になるでしょうか?!
2010年08月30日
武田信玄
NHK大河ドラマ『武田信玄』のDVDを借りてきました。
このシリーズは大河ドラマ史上でもトップレベルの視聴率を上げたとされています。
視聴率そのものは裏番組との相関関係もあるので、一概に“視聴率競争”をしても意味がありませんが、ともかく『武田信玄』がその時代の人たちに支持されたのは間違いないでしょう。
小生がこのシリーズが気になるのは、ストーリーテラー(語り部)が主人公の母親役(若尾文子)という点です。
「母」というのはその人に最も心情的に近くなるもので、その“目をとおして”語られると、親近感が出るのと同じくして「くどさ」がつきまとわります。
歴史という題材をドラマにしている以上、諸説があることが間違いないところですが、このストーリーテラーの言葉によって、その“諸説”に大きく色がつく可能性があります。
この手法も戦国時代だからこそかもしれませんね。
仮に、現代に近い歴史の題材で、母親をストーリーテラーにしたら反対論も巻き起こることでしょう。
例えば、名宰とも金脈政治のドンとも言われる田中角栄氏を大河ドラマの主人公にしたら…?!
まぁありえないことですが、敢えてこれを想像する場合に、その人の人生がどの程度現代に影響を与えているか…によって、諸説の扱い方も変わってくるかと思いますね。
そう言えば、『武田信玄』では若尾さんが冒頭、挨拶をしてこれから『息子晴信の物語を始めます…』としていました。
江藤新平の場合、妻の千代子さんにストーリーテラーを設定しようと考えていますので、参考にしたいと思っています。
このシリーズは大河ドラマ史上でもトップレベルの視聴率を上げたとされています。
視聴率そのものは裏番組との相関関係もあるので、一概に“視聴率競争”をしても意味がありませんが、ともかく『武田信玄』がその時代の人たちに支持されたのは間違いないでしょう。
小生がこのシリーズが気になるのは、ストーリーテラー(語り部)が主人公の母親役(若尾文子)という点です。
「母」というのはその人に最も心情的に近くなるもので、その“目をとおして”語られると、親近感が出るのと同じくして「くどさ」がつきまとわります。
歴史という題材をドラマにしている以上、諸説があることが間違いないところですが、このストーリーテラーの言葉によって、その“諸説”に大きく色がつく可能性があります。
この手法も戦国時代だからこそかもしれませんね。
仮に、現代に近い歴史の題材で、母親をストーリーテラーにしたら反対論も巻き起こることでしょう。
例えば、名宰とも金脈政治のドンとも言われる田中角栄氏を大河ドラマの主人公にしたら…?!
まぁありえないことですが、敢えてこれを想像する場合に、その人の人生がどの程度現代に影響を与えているか…によって、諸説の扱い方も変わってくるかと思いますね。
そう言えば、『武田信玄』では若尾さんが冒頭、挨拶をしてこれから『息子晴信の物語を始めます…』としていました。
江藤新平の場合、妻の千代子さんにストーリーテラーを設定しようと考えていますので、参考にしたいと思っています。
2010年08月30日
「東京」と江藤新平
日本の首都は東京ですが、明治維新時にはひょっとしたら「大阪が首都」になっていた可能性があります。
江藤新平は、「東京(江戸から改名)に首都を移す」ということに関しても関与をしていますが、国土交通省のWebサイトには明治維新での「東京遷都」のことが説明されています。
京都大学の佐々木克教授がこれらのことについて書いています。
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/onlinelecture/lec16.html
上記URLから一部転載
江戸への遷都を主張したのは幕臣の前島密です。彼は大久保利通の大坂遷都論を聞いて、そうではなくて江戸の方がいいという意見を述べています。これは全体として首都はどういうものであるべきか、都市景観の問題や将来の交通の問題、日本全体の中での位置関係、運輸・港湾の便なども考慮した非常にまとまったものとなっています。おもしろいのは、当時の江戸は世界の最大の都市であったわけですが、フランス革命があった頃のパリが 60万人ですから、その倍もある世界最大の都市、そのような自負もあるわけです。その都市が遷都によって荒れるにまかせてしまうのはよくないという考え方をしています。
このほかに江藤新平の東京遷都論といわれているものがあります。江藤新平が有名人なのでそのようにいわれていますが、草稿は大木喬任が書いたものです。ここで初めて「東京」という言葉が出てきます。「江戸城は急速に東京と被定」と書かれていますが、これがミソなのです。よく「江戸」という地名を「東京」という地名に変えたといわれますが、これは間違いです。この文章が東京遷都の実体をよく表しています。江戸城を中心とした江戸という空間を「東の京と定める」ということで、改めるのではないわけです。そして「東西両京」という表現に見られるように、西と東の都の両都論なのです。この段階ではまだ遷都論ではないのです。そしてこの文書の中に「東下(とうか)」という言葉が出てきますが、幕末の頃からこの言葉が盛んに使われるようになってきます。明らかに関東、江戸を下に見ているのです。その下に見ている江戸を東の京に格上げするということなのです。西の京と東の京の間を天皇が動くという形を想定しているのです。[転載了]
江藤新平は、「東京(江戸から改名)に首都を移す」ということに関しても関与をしていますが、国土交通省のWebサイトには明治維新での「東京遷都」のことが説明されています。
京都大学の佐々木克教授がこれらのことについて書いています。
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/onlinelecture/lec16.html
上記URLから一部転載
江戸への遷都を主張したのは幕臣の前島密です。彼は大久保利通の大坂遷都論を聞いて、そうではなくて江戸の方がいいという意見を述べています。これは全体として首都はどういうものであるべきか、都市景観の問題や将来の交通の問題、日本全体の中での位置関係、運輸・港湾の便なども考慮した非常にまとまったものとなっています。おもしろいのは、当時の江戸は世界の最大の都市であったわけですが、フランス革命があった頃のパリが 60万人ですから、その倍もある世界最大の都市、そのような自負もあるわけです。その都市が遷都によって荒れるにまかせてしまうのはよくないという考え方をしています。
このほかに江藤新平の東京遷都論といわれているものがあります。江藤新平が有名人なのでそのようにいわれていますが、草稿は大木喬任が書いたものです。ここで初めて「東京」という言葉が出てきます。「江戸城は急速に東京と被定」と書かれていますが、これがミソなのです。よく「江戸」という地名を「東京」という地名に変えたといわれますが、これは間違いです。この文章が東京遷都の実体をよく表しています。江戸城を中心とした江戸という空間を「東の京と定める」ということで、改めるのではないわけです。そして「東西両京」という表現に見られるように、西と東の都の両都論なのです。この段階ではまだ遷都論ではないのです。そしてこの文書の中に「東下(とうか)」という言葉が出てきますが、幕末の頃からこの言葉が盛んに使われるようになってきます。明らかに関東、江戸を下に見ているのです。その下に見ている江戸を東の京に格上げするということなのです。西の京と東の京の間を天皇が動くという形を想定しているのです。[転載了]
2010年08月30日
コンピューターグラフィックス
最近の大河ドラマでは、コンピューターグラフィックス(以下「CG」と言う)の技術は必要不可欠なもののようですね。
現在の大河ドラマのオープニングでもふんだんにこれが使われています。
音楽も今風ですし、“ドラマとしての完成度”は昔の大河ドラマよりも質が高いのかもしれません。
小生がちょっと気になるのは、CG技術がロケ地の選定にどう関わるか…ということです。
小生が大河ドラマで江藤新平を主人公にしたいのは、これをもって「佐賀の地域振興策」につなげたいからですが、CGの技術を駆使したら場合によってはロケを必要としない…という流れになるかもしれないと危惧しています。
大河ドラマのキャストは豪華で、人気の俳優が出演する場合、スケジュール管理が難しくなります。
その上、野外でのロケは自然の条件に左右されます。
天気などによって、ロケができない場合もありますし、撮影器具などの調達方法などのハードルもスタジオ撮影とは大きく異なります。
できれば「佐賀の地でロケをしてもらいたい…」と思っています。
佐賀のロケ地をより質がいいものに映し出すためのCGならば大歓迎なのですが…。
現在の大河ドラマのオープニングでもふんだんにこれが使われています。
音楽も今風ですし、“ドラマとしての完成度”は昔の大河ドラマよりも質が高いのかもしれません。
小生がちょっと気になるのは、CG技術がロケ地の選定にどう関わるか…ということです。
小生が大河ドラマで江藤新平を主人公にしたいのは、これをもって「佐賀の地域振興策」につなげたいからですが、CGの技術を駆使したら場合によってはロケを必要としない…という流れになるかもしれないと危惧しています。
大河ドラマのキャストは豪華で、人気の俳優が出演する場合、スケジュール管理が難しくなります。
その上、野外でのロケは自然の条件に左右されます。
天気などによって、ロケができない場合もありますし、撮影器具などの調達方法などのハードルもスタジオ撮影とは大きく異なります。
できれば「佐賀の地でロケをしてもらいたい…」と思っています。
佐賀のロケ地をより質がいいものに映し出すためのCGならば大歓迎なのですが…。
2010年08月29日
佐賀の乱の時系列
ブログを書く上で、プロットなどを整理するために「佐賀の乱(佐賀戦争)」の経過をウィキペディアから転載します。
ウィキペディア『佐賀の乱』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%B3%80%E3%81%AE%E4%B9%B1
[上記サイトから一部転載]
1873年(明治6)10月23日 明治6年政変。翌日江藤新平下野。
同12月10日 佐賀県権令岩村通俊上京。そのまま帰県せず県内の統制が低下する。
同12月23日 江藤派の青年士族らが征韓党を結成。
1874年(明治7)1月16日 征韓党士族が「征韓先鋒」の出願を決議。県に弘道館の貸与を強請。
同1月18日前後 中央より視察として大蔵大丞林友幸が到着。事態は深刻として政府に対処を要請。
同1月24日 佐賀県参事森長義、熊本鎮台の谷干城に県内に不穏な動きありとして対処を要請。谷は慎重な対応を求めつつも、山川浩に偵察を指令。
同1月25日 前参議江藤新平、佐賀に帰郷。征韓党の勢いが昂進する。
同1月28日 岩村通俊前権令の実弟岩村高俊が後任に任命される。岩村は長岡藩家老河井継之助の中立歎願を拒絶し、北越戦争の発端をつくった人物である。
同2月1日 憂国党に属する士族が官金預かり業者である小野組に強引に金談。店員ら逃亡。
同2月4日 政府、熊本鎮台司令長官谷干城に佐賀士族の鎮圧を命令。谷は拙速命令と批判。
同2月5日 政府の鎮圧命令を佐賀士族が電信局で探知。士族の議論が沸騰し、参事森長義ら他県出身の県官は逃亡。太政大臣三条実美、島義勇に直接鎮撫を要請。島は承諾。
同2月9日 内務卿大久保利通に九州出張命令。捕縛・処刑、兵力による鎮撫の権限を委任される。
同2月13日 岩村権令が熊本に到着。入県の護衛を同県人の熊本鎮台司令長官谷干城少将に依頼。この日、長崎に移っていた江藤も佐賀に戻り、「決戦の議」を起草。太政大臣三条実美の要請に応じて帰国した前侍従島義勇も同調し、征韓・憂国両党の結束が強まる。
同2月14日 岩村権令の強い要請により熊本鎮台が出動。陸海の2路に分かれ、山川浩少佐の左半大隊と岩村権令は海路を、佐久間左馬太少佐の右半大隊は陸路から佐賀に向かう。大久保内務卿、東京鎮台兵とともに横浜を出航。
同2月15日 岩村権令と鎮台兵、佐賀城の県庁に入る。佐賀士族軍は筑後川の防衛線で右半大隊の合流を阻みつつ、翌未明より城を包囲し砲撃。岩村らの乗船も拿捕される。
同2月17日 鎮台兵の苦戦を受け、政府は混乱が東京に波及することを防ぐため新聞に軍事関係の記事掲載を禁止。
同2月18日 岩村権令と山川少佐ら、食糧と弾薬が不足したため、包囲を突破して久留米に撤収。奥保鞏大尉(のち元帥)らが負傷し、将兵332名中137名戦死。
同2月19日 佐賀征討令が発せられる。大久保内務卿と野津鎮雄少将、鎮圧部隊を引き連れ博多に到着。
同2月20日 野津少将指揮の東京鎮台砲隊と大阪鎮台二個大隊、集結を終え、夕刻より行動開始。
同2月21日 前山清一郎の中立党が政府軍に合流。
同2月22日 鳥栖近郊の朝日山で佐賀士族と政府軍が激突。佐賀士族、後退し政府軍は長崎街道沿いに中原に進む。
同2月23日 政府軍、児玉源太郎大尉が重傷を負うなど激戦の末、寒水川を渡る。さらに吉野ヶ里遺跡付近の田手川に設けられた阻止線を突破。江藤は西郷隆盛の援軍を仰ごうと、征韓党幹部を連れて鹿児島へ脱出。また、島は島津久光に調停を要請するため、重松基吉と中川義純を鹿児島に派遣。神埼(神埼町)が焼失した。
同2月27日 政府軍、総攻撃開始。姉村、境原で激戦。三瀬峠も旧福岡藩士族の貫属隊に突破される。
同2月28日 憂国党幹部の木原隆忠と副島義高が政府軍の渡辺央少佐に休戦交渉。渡辺は降伏以外は受理しないとし、木原を捕虜とするとともに翌日総攻撃を行うと最後通牒。島らは鹿児島に脱出。外務少輔山口尚芳の率いる長崎から入った海軍の陸戦隊が無人の佐賀城を確保する。
同3月1日 大久保内務卿と政府軍、佐賀城に入城。征討総督嘉彰親王、近衛兵を率い東京出発。この日、江藤は宇奈木温泉で西郷隆盛に面会。支援を拒絶される。
同3月7日 島義勇、鹿児島で捕縛される。16日に佐賀に護送される。
同3月14日 総督嘉彰親王、佐賀に到着。
同3月29日 逃亡中の江藤が高知県甲ノ浦で捕縛される。
同4月5日 佐賀臨時裁判所設置。
同4月7日 江藤が佐賀に護送される。
同4月9日 江藤らの尋問開始。大久保、嘉彰親王に随従し傍聴。
同4月13日 江藤・島ら13名に死刑判決が下る。即日処刑(斬首。江藤・島は斬首のうえ梟首)される。その他、136人が懲役、240人が除族、7人が禁固の処分を受け、10713人は無罪とされた。
1919年(大正8)7月1日 大韓帝国の皇太子であった李垠と皇族方子女王の婚約発表による特赦令により、江藤や島など逆賊扱いされていた佐賀の乱の首謀者らが赦免される。
1920年(大正9) 地元佐賀に、佐賀の乱の慰霊碑が建立される。
ウィキペディア『佐賀の乱』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%B3%80%E3%81%AE%E4%B9%B1
[上記サイトから一部転載]
1873年(明治6)10月23日 明治6年政変。翌日江藤新平下野。
同12月10日 佐賀県権令岩村通俊上京。そのまま帰県せず県内の統制が低下する。
同12月23日 江藤派の青年士族らが征韓党を結成。
1874年(明治7)1月16日 征韓党士族が「征韓先鋒」の出願を決議。県に弘道館の貸与を強請。
同1月18日前後 中央より視察として大蔵大丞林友幸が到着。事態は深刻として政府に対処を要請。
同1月24日 佐賀県参事森長義、熊本鎮台の谷干城に県内に不穏な動きありとして対処を要請。谷は慎重な対応を求めつつも、山川浩に偵察を指令。
同1月25日 前参議江藤新平、佐賀に帰郷。征韓党の勢いが昂進する。
同1月28日 岩村通俊前権令の実弟岩村高俊が後任に任命される。岩村は長岡藩家老河井継之助の中立歎願を拒絶し、北越戦争の発端をつくった人物である。
同2月1日 憂国党に属する士族が官金預かり業者である小野組に強引に金談。店員ら逃亡。
同2月4日 政府、熊本鎮台司令長官谷干城に佐賀士族の鎮圧を命令。谷は拙速命令と批判。
同2月5日 政府の鎮圧命令を佐賀士族が電信局で探知。士族の議論が沸騰し、参事森長義ら他県出身の県官は逃亡。太政大臣三条実美、島義勇に直接鎮撫を要請。島は承諾。
同2月9日 内務卿大久保利通に九州出張命令。捕縛・処刑、兵力による鎮撫の権限を委任される。
同2月13日 岩村権令が熊本に到着。入県の護衛を同県人の熊本鎮台司令長官谷干城少将に依頼。この日、長崎に移っていた江藤も佐賀に戻り、「決戦の議」を起草。太政大臣三条実美の要請に応じて帰国した前侍従島義勇も同調し、征韓・憂国両党の結束が強まる。
同2月14日 岩村権令の強い要請により熊本鎮台が出動。陸海の2路に分かれ、山川浩少佐の左半大隊と岩村権令は海路を、佐久間左馬太少佐の右半大隊は陸路から佐賀に向かう。大久保内務卿、東京鎮台兵とともに横浜を出航。
同2月15日 岩村権令と鎮台兵、佐賀城の県庁に入る。佐賀士族軍は筑後川の防衛線で右半大隊の合流を阻みつつ、翌未明より城を包囲し砲撃。岩村らの乗船も拿捕される。
同2月17日 鎮台兵の苦戦を受け、政府は混乱が東京に波及することを防ぐため新聞に軍事関係の記事掲載を禁止。
同2月18日 岩村権令と山川少佐ら、食糧と弾薬が不足したため、包囲を突破して久留米に撤収。奥保鞏大尉(のち元帥)らが負傷し、将兵332名中137名戦死。
同2月19日 佐賀征討令が発せられる。大久保内務卿と野津鎮雄少将、鎮圧部隊を引き連れ博多に到着。
同2月20日 野津少将指揮の東京鎮台砲隊と大阪鎮台二個大隊、集結を終え、夕刻より行動開始。
同2月21日 前山清一郎の中立党が政府軍に合流。
同2月22日 鳥栖近郊の朝日山で佐賀士族と政府軍が激突。佐賀士族、後退し政府軍は長崎街道沿いに中原に進む。
同2月23日 政府軍、児玉源太郎大尉が重傷を負うなど激戦の末、寒水川を渡る。さらに吉野ヶ里遺跡付近の田手川に設けられた阻止線を突破。江藤は西郷隆盛の援軍を仰ごうと、征韓党幹部を連れて鹿児島へ脱出。また、島は島津久光に調停を要請するため、重松基吉と中川義純を鹿児島に派遣。神埼(神埼町)が焼失した。
同2月27日 政府軍、総攻撃開始。姉村、境原で激戦。三瀬峠も旧福岡藩士族の貫属隊に突破される。
同2月28日 憂国党幹部の木原隆忠と副島義高が政府軍の渡辺央少佐に休戦交渉。渡辺は降伏以外は受理しないとし、木原を捕虜とするとともに翌日総攻撃を行うと最後通牒。島らは鹿児島に脱出。外務少輔山口尚芳の率いる長崎から入った海軍の陸戦隊が無人の佐賀城を確保する。
同3月1日 大久保内務卿と政府軍、佐賀城に入城。征討総督嘉彰親王、近衛兵を率い東京出発。この日、江藤は宇奈木温泉で西郷隆盛に面会。支援を拒絶される。
同3月7日 島義勇、鹿児島で捕縛される。16日に佐賀に護送される。
同3月14日 総督嘉彰親王、佐賀に到着。
同3月29日 逃亡中の江藤が高知県甲ノ浦で捕縛される。
同4月5日 佐賀臨時裁判所設置。
同4月7日 江藤が佐賀に護送される。
同4月9日 江藤らの尋問開始。大久保、嘉彰親王に随従し傍聴。
同4月13日 江藤・島ら13名に死刑判決が下る。即日処刑(斬首。江藤・島は斬首のうえ梟首)される。その他、136人が懲役、240人が除族、7人が禁固の処分を受け、10713人は無罪とされた。
1919年(大正8)7月1日 大韓帝国の皇太子であった李垠と皇族方子女王の婚約発表による特赦令により、江藤や島など逆賊扱いされていた佐賀の乱の首謀者らが赦免される。
1920年(大正9) 地元佐賀に、佐賀の乱の慰霊碑が建立される。
2010年08月29日
江藤新平の妻、千代子さん
小生が考えるNHK大河ドラマ「江藤新平」のストーリーテラーは妻の千代子さんですが、江藤とは従姉妹同士で年上女房です。
1974年に佐賀新聞で江藤の孫、江藤冬雄さんが『江藤家をめぐる人々』を連載されていましたが、このシリーズの最初に『祖母の思い出』がつづられています。
この祖母が千代子さんですが、かくしゃくとしたご婦人で85歳で亡くなれたそうです(大正6年5月27日)。
前回のブログで書いた明治44年の江藤の表彰ですが、その際、衆議院で可決されましたが、「復位爵位」も両院で通過したものの枢密院で井上馨の強行な反対によって上奏をやめたと書かれています。
井上馨と江藤とは、予算問題で激しく闘いました。
江藤が出した「裁判所増設の儀」での確執、さらには「尾去沢銅山事件」での対立もあって、井上の江藤家への恨みは彼の晩年まで続いたのかもしれません。
ウィキペディア『尾去沢銅山事件』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%8E%BB%E6%B2%A2%E9%89%B1%E5%B1%B1
千代子さんは6人の子供がいましたが、4人の息子にはすべて先立たれ、同居していた冬雄さんによると以下のように表現されていました。
『父(江藤新作)の在世中は、家の中に笑い声も時々聞こえていたが、父が死んでからは、それこそ家の中は“深山幽谷”のごとしである。祖母(千代子さんこと)は毎日、火ばちの前に伏し加減に黙って座している。何を思っているのかわからない。母をはじめわれわれ子ども、歩くのも忍び足、高い声を出すことも禁物、歌を歌うなどもってのほか、故にわが兄弟姉妹全部、学校の成績、唱歌は丙の下である。まぁ、江藤家というものは、沈鬱陰惨、荒涼の見本みたいなものであった』(佐賀新聞1974年2月22日)
千代子さんと一緒に住んでいた江藤冬雄さんのお話なので、大変興味深く記事を読ませていただきました。
1974年に佐賀新聞で江藤の孫、江藤冬雄さんが『江藤家をめぐる人々』を連載されていましたが、このシリーズの最初に『祖母の思い出』がつづられています。
この祖母が千代子さんですが、かくしゃくとしたご婦人で85歳で亡くなれたそうです(大正6年5月27日)。
前回のブログで書いた明治44年の江藤の表彰ですが、その際、衆議院で可決されましたが、「復位爵位」も両院で通過したものの枢密院で井上馨の強行な反対によって上奏をやめたと書かれています。
井上馨と江藤とは、予算問題で激しく闘いました。
江藤が出した「裁判所増設の儀」での確執、さらには「尾去沢銅山事件」での対立もあって、井上の江藤家への恨みは彼の晩年まで続いたのかもしれません。
ウィキペディア『尾去沢銅山事件』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%8E%BB%E6%B2%A2%E9%89%B1%E5%B1%B1
千代子さんは6人の子供がいましたが、4人の息子にはすべて先立たれ、同居していた冬雄さんによると以下のように表現されていました。
『父(江藤新作)の在世中は、家の中に笑い声も時々聞こえていたが、父が死んでからは、それこそ家の中は“深山幽谷”のごとしである。祖母(千代子さんこと)は毎日、火ばちの前に伏し加減に黙って座している。何を思っているのかわからない。母をはじめわれわれ子ども、歩くのも忍び足、高い声を出すことも禁物、歌を歌うなどもってのほか、故にわが兄弟姉妹全部、学校の成績、唱歌は丙の下である。まぁ、江藤家というものは、沈鬱陰惨、荒涼の見本みたいなものであった』(佐賀新聞1974年2月22日)
千代子さんと一緒に住んでいた江藤冬雄さんのお話なので、大変興味深く記事を読ませていただきました。
2010年08月29日
江藤新平の表彰
明治44年の衆議院で前参議江藤新平の表彰が可決されたことは以前のブログでも書きました。
帝国議会の議事録をWebサイトで調べたところ、下記のページが出てきました。
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/cgi-bin/TEIKOKU/swt_list.cgi?SESSION=29711&SAVED_RID=6&MODE=1&DTOTAL=6&DMY=141
上記のサイトで「明治44年3月18日」の議事録には『前参議司法卿江藤新平表彰ニ関スル建議案員会録(第3回)で、島田三郎議員は江藤の業績について長々とそのすごさを述べています。
大河ドラマ「江藤新平」のシナリオでは、この島田氏の演説は大いにある勇気を与えるものとして表現されるでしょうね…。
2010年08月29日
岩村三兄弟
江藤新平を主人公にNHK大河ドラマをするとなると、「岩村三兄弟」は大きな役割を担うでしょう…。
三兄弟がいずれも江藤や佐賀に縁があるというのも不思議な縁だと思います。
岩村通俊が長男で、次男は林有造(林家へ養子)、岩村高俊は三男です。
三人とも割りとこの時代にしては長生きをしているんですよねぇ…。
ウィキペディア『岩村通俊』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E9%80%9A%E4%BF%8A
ウィキペディア『林有造』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E6%9C%89%E9%80%A0
ウィキペディア『岩村高俊』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E9%AB%98%E4%BF%8A
長男の通俊は、「佐賀の乱(佐賀戦争)」で梟首になった島義勇の後の北海道の開拓使判官となり、その後、明治6年(1874年)7月佐賀県権令となり、後任は弟の高俊です。
高俊は、佐賀の乱当時の権令で江藤や島と戦いました。
次男の有造は、江藤が最後に会いに行った人物です。
佐賀の乱に破れた江藤は西郷隆盛に決起を訴えるために南下し(鹿児島へ)、その後、林に会いに土佐に渡っています。
岩村三兄弟の中で最も長生きしたのは、次男有造の79歳です。
三兄弟がいずれも江藤や佐賀に縁があるというのも不思議な縁だと思います。
岩村通俊が長男で、次男は林有造(林家へ養子)、岩村高俊は三男です。
三人とも割りとこの時代にしては長生きをしているんですよねぇ…。
ウィキペディア『岩村通俊』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E9%80%9A%E4%BF%8A
ウィキペディア『林有造』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E6%9C%89%E9%80%A0
ウィキペディア『岩村高俊』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E9%AB%98%E4%BF%8A
長男の通俊は、「佐賀の乱(佐賀戦争)」で梟首になった島義勇の後の北海道の開拓使判官となり、その後、明治6年(1874年)7月佐賀県権令となり、後任は弟の高俊です。
高俊は、佐賀の乱当時の権令で江藤や島と戦いました。
次男の有造は、江藤が最後に会いに行った人物です。
佐賀の乱に破れた江藤は西郷隆盛に決起を訴えるために南下し(鹿児島へ)、その後、林に会いに土佐に渡っています。
岩村三兄弟の中で最も長生きしたのは、次男有造の79歳です。
2010年08月29日
山中と香月
佐賀の乱(佐賀戦争)では、江藤新平ともに刑死した優秀な人材がいます。
中でも、山中一郎、香月経五郎はもし、ここで命を落とさなかったら間違いなくその後の明治政府において重要な職責を担ったと思います。
ウィキペディア『山中一郎』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E4%B8%80%E9%83%8E_(%E4%BD%90%E8%B3%80%E8%97%A9%E5%A3%AB)
ウィキペディア『香月経五郎』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%9C%88%E7%B5%8C%E4%BA%94%E9%83%8E
江藤は、佐賀の乱で“武装解除”した後、西郷隆盛と林有造に会いに行っています。
この際に山中、香月の両名も同行していますが、これらの“ドラマ”についてもしっかりと描いていきたいと思っています。
中でも、山中一郎、香月経五郎はもし、ここで命を落とさなかったら間違いなくその後の明治政府において重要な職責を担ったと思います。
ウィキペディア『山中一郎』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E4%B8%80%E9%83%8E_(%E4%BD%90%E8%B3%80%E8%97%A9%E5%A3%AB)
ウィキペディア『香月経五郎』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%9C%88%E7%B5%8C%E4%BA%94%E9%83%8E
江藤は、佐賀の乱で“武装解除”した後、西郷隆盛と林有造に会いに行っています。
この際に山中、香月の両名も同行していますが、これらの“ドラマ”についてもしっかりと描いていきたいと思っています。
2010年08月28日
第3回 ~プロット~
幕末の世の中
混迷の時代
京都
エピソード
タイトル 音楽
決心
脱藩
いざ京都へ
桂小五郎との出会い
京都見聞録
江藤新平が見た幕末
幕末の他藩の志士らの活動
吉田松陰
高杉晋作
西郷隆盛
尊皇攘夷
開国論
混迷の時代
京都
エピソード
タイトル 音楽
決心
脱藩
いざ京都へ
桂小五郎との出会い
京都見聞録
江藤新平が見た幕末
幕末の他藩の志士らの活動
吉田松陰
高杉晋作
西郷隆盛
尊皇攘夷
開国論
2010年08月28日
3つのストーリーが同時進行 ~アモーレス・ペロス~
プロットはシナリオを書く上で重要な作業ですが、小生が考えているのは「矛盾」がないようにつながること…。
これは、ある意味パズルを組み合わせるようなものかと思います。
これまで見た映画の中で“プロットの妙”を一番感じたのが『アモーレス・ペロス(AMORES PERROS)』という映画です。
メキシコ映画ですが、一つの事故(自動車事故)を基点として、3つのストーリーが同時進行で動き出します。
そして、主人公も3人いて、それぞれの人生を映し出しています。
ここまでのシナリオを書けるのは、プロ中のプロでしょうが、小生の中では教科書的な作品であり、コトあるごとにこの映画を見ています。
これは、ある意味パズルを組み合わせるようなものかと思います。
これまで見た映画の中で“プロットの妙”を一番感じたのが『アモーレス・ペロス(AMORES PERROS)』という映画です。
メキシコ映画ですが、一つの事故(自動車事故)を基点として、3つのストーリーが同時進行で動き出します。
そして、主人公も3人いて、それぞれの人生を映し出しています。
ここまでのシナリオを書けるのは、プロ中のプロでしょうが、小生の中では教科書的な作品であり、コトあるごとにこの映画を見ています。
2010年08月28日
プロットとは?!
ウィキペディアによると、『プロット』の説明に以下のようなことを書いていました。
参照;ウィキペディア『プロット』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88_(%E7%89%A9%E8%AA%9E)
上記URLから一部転載
文芸評論では、物語の中で起きている出来事が時間に沿って並べられたものが「ストーリー」であるのに対して、その出来事を再構成したものを「プロット」と呼ぶ。プロットは時間軸に沿っているとは限らないが、出来事の因果関係を示している。例えば「妻が重い病気になった。夫は毎日泣き暮らすようになった」はストーリー、「夫は毎日泣き暮らすようになった。理由がわからなかったが、妻が重い病気になったからだとわかった」はプロットである、などと説明されることが多い。
プロットとストーリーについては、イギリスの作家E・M・フォースターが1927年に発表した『小説の諸相』での解説が有名である。
元々は、単に筋に関連する出来事がひとつの形を形成したもののことをプロットと呼んだ。紀元前4世紀、古代ギリシアの哲学者アリストテレスが『詩学』の中で既に「始め・中・終り」の3つに区分するという基本的なプロットについて述べている。この基本的な意味でのプロットという用語は、現代でも小説などの創作の現場でよく使われ、物語を作るときの設計図・構想のことを指す。物語のあらすじ、登場人物の設定や相関図、事件、小道具、世界観などがプロットに含まれる。特にエンターテインメントや長編小説などの構成力を必要とする創作では、プロットを練ることが不可欠であると考えられている。
ただし、スティーヴン・キングのように、プロット無しで小説を書き、大成した作家もいないわけではない。[転載了]
参照;ウィキペディア『プロット』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88_(%E7%89%A9%E8%AA%9E)
上記URLから一部転載
文芸評論では、物語の中で起きている出来事が時間に沿って並べられたものが「ストーリー」であるのに対して、その出来事を再構成したものを「プロット」と呼ぶ。プロットは時間軸に沿っているとは限らないが、出来事の因果関係を示している。例えば「妻が重い病気になった。夫は毎日泣き暮らすようになった」はストーリー、「夫は毎日泣き暮らすようになった。理由がわからなかったが、妻が重い病気になったからだとわかった」はプロットである、などと説明されることが多い。
プロットとストーリーについては、イギリスの作家E・M・フォースターが1927年に発表した『小説の諸相』での解説が有名である。
元々は、単に筋に関連する出来事がひとつの形を形成したもののことをプロットと呼んだ。紀元前4世紀、古代ギリシアの哲学者アリストテレスが『詩学』の中で既に「始め・中・終り」の3つに区分するという基本的なプロットについて述べている。この基本的な意味でのプロットという用語は、現代でも小説などの創作の現場でよく使われ、物語を作るときの設計図・構想のことを指す。物語のあらすじ、登場人物の設定や相関図、事件、小道具、世界観などがプロットに含まれる。特にエンターテインメントや長編小説などの構成力を必要とする創作では、プロットを練ることが不可欠であると考えられている。
ただし、スティーヴン・キングのように、プロット無しで小説を書き、大成した作家もいないわけではない。[転載了]